|
タクシー部事務局長からの提案・提起
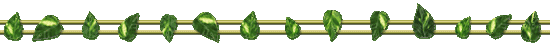
本日はお忙しい中、またお疲れの中、交通運輸一般労働組合主催のタクシー乗務員集会に、ご参加下さり大変ありがとうございます。
開始そうそうの時間を戴き、今日のタクシー事情に関する、疑問・不満・意見などを、私から少々述べさせて頂きます。
そのあと、皆さんが普段考えている、タクシーの不満・意見など、大いに語り合う時間を用意しておりますので、その時は、どうぞご協力の程よろしく、お願い致します。
すでに皆さんご存知のように、2002年2月に行政と、一部の識者が無理押しした「タクシーの規制緩和」が施行され、5年目に突入した今年「勘定合って銭是らず」のことわざの如く、理論と現実とが一致しないことが明白になってきており、いまや私たちタクシーを取り巻く全ての環境を悪化させ、テレビ・新聞をも巻き込み社会問題化しております。
「規制緩和」とは、一口でいうと大企業優先の法であると、私は日頃から思っております。政府が「構造改革」の名で行ってきた異常なまでの大企業中心主義の政治、その結果何でも有りの「ルールなき資本主義」の悪が今まさに、吹き出しているところです。
その悪は大きく分けると三っあると考えられます。
一っには非正規雇用者の急増など人間らしい雇用の破壊。
二っ目は年金・介護に続き老人医療費の値上げなど社会保障の破壊。
三っ目は、庶民には増税。大企業・大資産家に減税という全く逆な税制度。
この三悪がもたらした結果が、こんにちの「格差社会」と、貧困の広がりを強めたわけです。
特に「格差社会」と貧困の広がりは、一大社会問題となり、マスメディァも深刻な現実を伝え出しました。小泉首相は最初に「言われているほど格差はない」と言いつつも、それが通用しなくなると「格差が出るのは悪いことではない」と開き直り、それが批判されると「経済状況が良くなれば解決する」と責任逃れを計っているのです。
政府は「景気は上向き、回復傾向にある」といっているが、私たちタクシーから見ればどこでどう景気が回復しているか、全く見えてきません。
政府の出したこの十年間の統計を見てみると、年収別に増えている階層が二つあるのです。年収二百万円以下の低所得者層が24%も増え、一千万人に達しました。その一方で年収二千万円を超える高額所得者層が30%増えましたが、この層は数では二十万人とごくわずかです。
このように、ごく一部の大企業と大資産家が富めば富むほど、貧困層が広がり、格差が深刻になるということが、現実に起こっていることなのです。現に、国内の労働者の3人に一人、青年と女性の二人に一人はパート、派遣など非正規雇用のもとで働いています。友人・知人・家族など、皆さんの廻りにも非正規雇用のもとで働いている人が、数多くいるのではないでしょうか。
非正規労働者の8割が年収150万円以下という低賃金、しかも無権利状態のもとで、正社員と同じ仕事の責任を持たされながら、忌引休暇も年休も保障されず社会保険にも加入できず、絶え間ない解雇の不安にさらされています。
つい先日も、習志野市内にある大手スーパーにおいて、勇気あるパート主婦が労働改善を求め、労働局に訴え出たことが新聞報道されたばかりです。
1990年以降、上場企業の9割は、正規雇用の労働者に、成果主義賃金なるものを導入してきました。労働者間の競争をあおり立て、命も健康をもすりつぶす成果主義賃金は、目標を100%達成したとしても「並」の賃金にしかならず、ほとんどの人が達成できず賃下げという結果が押しっけられています。
『年齢にかかわらず、賃金が下がるシステムとなっているのです。』
これは、成果主義賃金が、もともと総額人件費の削除を目的として導入されていることからくる、必然的な結果であります。
「成果」を出すために残業をする。しかしその残業を申告すれば、残業をしなければ「成果」が出せないのは能力が低いからだとされ「評価」が下がるのです。ゆえに申告したくても、申告ができないのであります。
こうして、成果主義賃金は、耐え難き長時間過密労働・「サービス残業」を蔓延する、悪の温床になっているのです。
さて、今まで私が述べて来た事すべてが、私たちタクシーにも、当てはまるとは思いませんか。「タクシーの規制緩和」は、大企業優先のためにあると言っても過言ではありません。新規参入・増車OK,料金の値下げ競争・割引運賃など、どれを取っても運転手に、得することは、ありません。
そして向こう5年間、このままの状態でタクシーがあるならぱ、中小企業のタクシー会社は大企業に吸収されてしまいます。
こうなったら運転手には、会社を選ぶ余裕などありません。
常に会社の言うがままに、低賃金で今よりも一層長時間、サービス残業しなければならなくなり、有給休暇など規約上あったとしても取ることが出来ず、会社は努力しろ努力しろと芦収の上がらない運転手を、はやし立てるのであります。
それ等に、耐えることが出来ない運転手は、邪魔者扱いされ、使い捨てにされるのです。
運転手は陸に上がったカッパ同様、つぶしが利きませんので、ストレスを蓄えながら我慢を虐げられるのです。
タクシー運転手の平均年齢は、今や58歳、高齢化が進み運転手の4割が60歳代70歳台で要するに年金組で締めらています。
皆さんも一度客待ちの時、前後左右をじっくり観察してみてはいかがでしょうか。自分も含め、廻りはジジ・ババぱかりですから。
最近、福祉・介護タクシーが増えて参りました。この福祉・介護タクシーにも、あと僅かで自分自信が世話になると患われる60代70代の人達が、運転手として雇用される時代がきているのです。高齢になればなるほど反射神経が鈍くなってきます。
このジジ・ババが、成果主義賃金・累進歩合賃金のために、早朝から深夜までハンドルを握るのでありますから、交通事故が増えるのは当たり前なのです。
そして、運良く足切り達成したとしても、「賃金の格差社会」の底辺に位置しているタクシーの月額報酬は、手取り18万円前後。とても人並みの生活は、できる訳がありません。生活費の一部の足しにと、軽い気持ちでサラ金から借りたお金。やがて一件が二件、三件となり、サラ金に返済のためにまた借りてしまう。
この繰り返しで、返済のめどが立たなくなり多重債務者になってしまうのです。
ある若手弁護士のところには、このような借金問題を抱え相談に来る、タクシー運転手が後を絶たないと言っておりました。
ある新聞に「将来、自分の子供にタクシー運転手の仕事を勧めますか」という、興昧深いアンケート調査が、現役タクシー運転手を対象に行われた、との記事が掲載されていました。その結果、9割の運転手が「ノー」と答えたそうです。
「一体誰がこんなタクシーにしていまったのか」
「タクシーをどうしてこんな状態にしてしまわなければならなかったのか」
「タクシーの規制緩和」を推した役人や、高見から賢者の如く無責任にもの言う第三者に聞いてみたいものです。
タクシー運転手は、規制緩和以前に利用客減少を敏感に察知しており、これが新規参人・増車となれば、ますますタクシーでの生活安定が脅かされることを予知しておりました。行政は、競争を促進して需要を増やし、利用者の利便性向上と事業拡大を目論見ました。
目論見どうり車両台数は増え、運賃の値下げ競争が起きましたが、需要は増えなかったのです。
その結果、運転手の収入は減り続け、無理な運転による交通事故が増大したわけです。
行政は、この責任逃れのために、今度はタクシー事業をどう正常化するか考えました。国土交通省・大学教授・労使などの一部代表からなる、交通政策審議会なるものを設け、悪質な事業者の退出を促す仕組みや、運転者の資質確保などをメインに検討し順次、法制化に着手する方向でいます。
しかし、その内容は、後に述べますが、運転手の立場としては、全く期待できないものであります。「規制緩和」がどれほど混乱を招いているかを、委員会は、認識していないのです。
また私たちタクシー運転手の苦悩を知り得ない、第三者があれやこれやと取り決めたところで真の解決にはならないと、私は思うのであります。
なぜなら、肝心要の運転手の累進歩合制賃金問題に、メスが入っていないのです。いかに縞麗事をたくさん並べようと、累進歩合制賃金問題を是正しない限り、これから先、運転手の資質、人手不足は解消しないと私は思っております。
さて、人間が困難に遭遇した時、三つのタイプがあるといわれております。
団塊の世代に生きてタクシー運転手となり、「俺はもうすぐ定年だから」とか「何をやっても変わらない」と行動する前から物事を諦めてしまう、臆病な人。
また人一倍愚痴を言って、現在置かれている環境に不平・不満を持ち、人に同意を求める卑怯な人。
三つ目は先程、某スーパーのパート主婦が労働改善を求め、行動を起こした話をしましたが、少しでも一歩前に足を踏み出す、勇気ある人です。
今日ここに集った方は、もちろん人変勇気ある人だと私は思っております。
交通政策審議会メンバーの中にも、ただ一人勇気ある委員がおりました。
東京にある、タクシー会社・社長ですが、その委員の発言内容は「タクシー問題の真の原因は歩合給そのものにあります。これにメスを入れるのが最重点課題と捉え、最低賃金は固定し、プラスアルファなど給与体系を固定化していくべきだ」と主張しておりました。まさにその通りだと、私は思います。
しかし、出る杭は打たれるのことわざ通り、この主張に対し、「運転手の仕事ぶりを評価するには歩合制が必要だ。労使間でこんにちのタクシーを維持してきた」また「長い歴史の中で、労使によって出来上がったシステム」と反論している臆病で、卑怯な委員がいるのも事実です。
ここで、委員会報告書の一部を、紹介させていただきます。
タクシーの将来ビジョンとして、「総合生活移動産業」へ脱皮を促進する、基本方針が示されました。
一つは、タクシーは公共交通機関で顧客サービス業である。
二つ目は、高齢者ら、交通弱者の移動手段で、福祉・育児など地域密着型生活支援をしていく。
そして、具体的な施策案として、安全・安心なサービスの提供、運転者の表彰制度・魅力ある職場づくりをする。
事業者及び運転者のランク制度を設け、乗り場の差別化を検討する。
これはどういうことかというと (事業者ランク制によって、優良事業者が優先的に駅前などの好位置に乗り入れ出来るようにする、ということです)
また、労働関係法令違反への対応強化では、厚生労働省との連携で、最低賃金相互通報などの実施状況を踏まえる。
累進歩合制度廃止の趣旨を過労運転防止とあわせ徹底する。
以上、おおまかに報告内容の一部を紹介しましたが、皆さん如何でしたか。
これが、新しい時代の、新しいタクシーの在り方を検討している、交通政策審議会での役人・学者及びタクシー会社・社長たちの議論した結果だそうです。
国土交通省はこれらを法制化しようとしているのです。
私から言わせると、あまりにも幼稚な意見です。
どこがどう、新しいタクシーの在り方なのか、全く理解出来ません。
委員会メンバーは、ごく普通に街中を走っているタクシーを、はたして利用しているのだろうか、名も無い運転手に耳を傾けたことがあるのだろうか、私は疑問に思います。
私は、タクシーがサービス業である。などとは運転手になった時から知っています。普段から高齢者も乗せていますし、手足や、目の不自由な人も乗せています。
事業者・運転手にランク制度を設けるなどとは、まさに成果主義のなにものでも無い。
そのことが、交通事故増加の原因であることが、解らないのであろうか。
最低賃金の会社をチクリ合うとか・累進歩合廃止など全く、委員会の空言としか思えません。
ゆえに、委員会報告内容は、私が思うところ、大企業が優良事業者となり、弱小企業を弾き出し、仕事が出来やすいようにする「タクシーの規制緩和」以外、何物でもないと、私は考えます。
委員会メンバーのタクシー会社・社長たちは、知識者という仮面をかぶり、見栄っ張りの欲張りで、なんと無責任な人達の集まりなのであろうか。
自分たちで最低賃金・累進歩合廃止を法制化しようと決めておきながら、舌も乾かぬうちに歩合給の見直しは、長年労使間で決めたシステムだからやめられない、といっているのであります。
人手不足・運転手の高齢化・資質の問題すべての原因は、累進歩合給によるものだと、理解しているはずだが、先人をきってボロい儲けが出る累進歩合給システムを変えようとはしない。
そのくせ、車両のグレードアップはする、IT時代に呼応したGPS・ドライブレコーダーなどは、金が掛かっても取り付ける。金を掛けることが利用者へのサービスと勘違いしているのではなかろうか。
確かに今の時代、利用者へのサービスとして、カード決済機器・カーナビ位は必要だと思うが、もっと他に利用者が求めているものが、あると私は思います。
それは、運転手の極当たり前の接客態度ではなかろうか。
利用者も運転手に気兼ねすることなく、気持ち良くタクシーに乗ることが出来れば、それ以上のサービスは、求めていないのでは、ないだろうか。
運転手の接客態度がなぜ悪くなるのか原因を突き詰め、その根本原因の一つを是正することによってタクシー問題の大半は解決出来るのではないでしょうか。
委員会では、運転手の資質ぱかりを求めているが、と同時に、経営者側が、質を正していかなけれぱ本当の意味での、タクシー問題解決にはならないと、私は思っています。
累進歩合給は労働基準法違反です。
千葉労働局が行った労働条件自主点検において、累進歩合制度を採用しているかどうか308事業所に質問したところ、21事業所で累進歩合制度を採用している、との回答があったそうです。
私から見れぱ、この回答を素直に受け入れることは出来ません。
足切りを達成しなけれぱ、極端に給与が下がり、最低賃金を割る会社もあります。足切りを達成する為には借金をしてでも、足切り額までブッコミをする、運転手が数多くおります。
このことが、累進歩合制度でなければ、何と言うのでありましょうか。
殆どの会社は、必ず利益が出る足切り制度があり、累進歩合制度を採用しています。
会社の本音は、勿論、累進歩合制度であり、外に向かっての、たてまえは、給与明細を見てみると解る通り、基本給から始まって深夜残業手当まで、その月の本人%取分を見事なまでに、ふり分け、基本給制度であると、大ボラを吹いているのであります。
この最悪の制度を変えずして、タクシーの正壷化など有り得ません。
今年6月に交運労として、労働局・陸運支局・県タクシー協会などへ、規制緩和即時中止、累進歩合を廃止して月給制に移行へ、との要請行動を行って参りましたが、役人の何とも頼りない回答が帰ってくるぱかりで、ガッカリしました。と同時に、タクシー運転手の不利な環境を変えて行くには、やはり運転手自らが、立ち上がらなけれぱ、何も解決しない事がわかりました。
そのスタートとして、タクシー運転手の集いを今年4月22日に開催。
そして6月1日から、「目指せ!賃金体系の改善」というビラを、千葉県下の労働組合及び、タクシー運転手に配付して、きょう二度目のタクシー運転手の集いを開催したわけです。
タクシー会社及び労働組合は違えども、私たち運転手の要求は一っだと思っております。
最近、国会でもタクシーの累進歩合制度にっいての質問が取り上げられました。
また、先程のタクシー会社・社長自らの、歩合給にメスを入れ・る事が大事であるとの発言にも必ずや、一人・二人と呼応する事業者が、出てくると私は信じています。
テレビ・新聞・世論までもが、タクシーの「賃金の格差社会」の広がりを認めている今「好機、逸っすべからず」です。私たちタクシーでの「生活の安定」を目指すためには、勇気ある人の「数の力」が絶対条件であります。
今日ここに集った皆さん一人一人の勇気という「二文字」の波を、一波・二波と大海原に押し出し、その勇気ある人の「数の力」を持って、私たちタクシー運転手を、苦しめる累進歩合制度の廃止、そして安心して働ける、保障給を確保した月給制への移行を、関係各省に訴えていこうと患っております。
ただ何もせずに手をこまねいていては、タクシーの改革は出来ません。
どうか皆さん、タクシーの環境は私たちタクシー運転手の手で必ずや、改革しようではありませんか。
交通運輸一般労働組合 タクシー部
事務局長 西出 豊 |
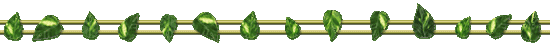
|